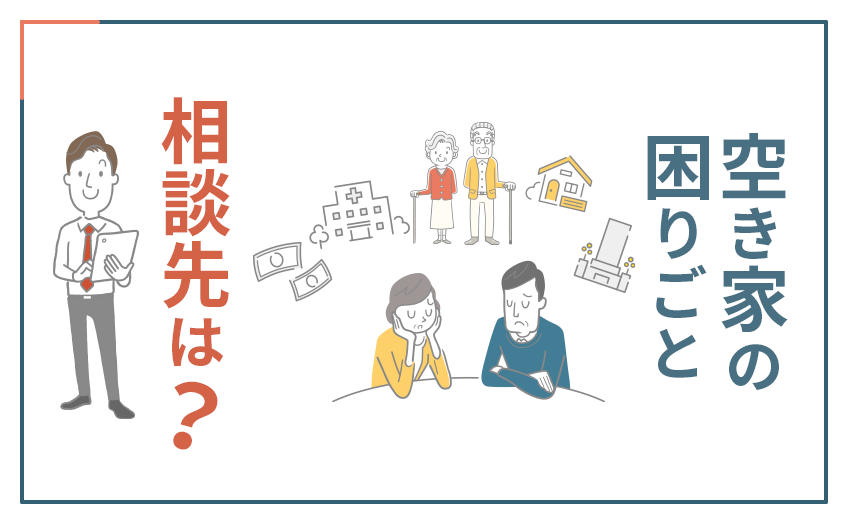親が亡くなり、実家を相続することになるケースは、多くの人に訪れます。実家を兄弟間などで共有名義にするケースも多くありますが、結論から申し上げると、共有名義で相続することはおすすめできません。
今回のコラムでは、実家を共有名義で相続するリスクとその対策について紹介します。ぜひ参考にしてください。
不動産の共有名義とは
一つの不動産を複数の人で所有している状態を共有名義といいます。不動産は現金のように均等に分けることは難しいため、不動産の所有権を均等に分けることで平等に分割する方法があります。家の所有者である父親が亡くなって、母親も既に亡くなっている場合は子どもが相続人になります。例えば、子どもが3人いれば所有権を3分1ずつに分割して、共有名義で相続登記を行うということが可能です。それぞれの子どもが持つ所有権の割合を「持ち分」といいます。
共有名義のメリットとしては、不動産であっても複数人で公平に分けられる点が挙げられます。
共有名義のリスク・デメリット
空き家を共有名義で相続することは公平感が強く、一見よい方法のように思われるかもしれません。しかし、共有名義には以下のようなデメリットやリスクがあります。
管理の方法でもめやすい
共有名義にして、空き家を今の状態のまま維持するにしても、管理は必要になります。その管理をどのように行うのか、誰が行うのか、その際に発生した費用負担はどうするのかなど、さまざまな問題が発生します。共有名義とは、名義人全員が平等に責任を持っている状態です。手間と費用を平等に負担することは困難であることは意識しておく必要があるでしょう。
売却・賃貸化・大規模修繕ができない
相続した空き家について、「売却して現金化したい」「賃貸物件にしたい」「リフォームして自分が住みたい」というように共有名義人の中で意見が割れてしまうケースがあります。雨漏りの修理や賃貸化(賃貸で貸す)などは過半数以上の持ち分の同意があれば行えますが、売却や間取りが変わるような大規模リフォームなどは、共有名義人全員の同意がないと行うことはできません。空き家を共有名義で相続するという平等感を重視した結果、誰の希望も通らず、全員が不満を抱えてしまう可能性が大いにあります。
また、仮に売却をしようと話が決まっても、売却価格や値下げのタイミングを決めるのにも全員の同意が必要になります。
固定資産税の支払いトラブルが起きやすい
毎年1月1日時点での所有者に支払いが求められる固定資産税は納税通知書が届き、それをもとに支払います。共有名義で空き家を相続した場合でも、通知書は分割されず、代表者に送付されます。そのため、代表者が一旦立て替えることになるケースが多く、これが原因で共有名義人の間で金銭トラブルに発展する可能性があります。
新たな相続でさらに複雑化する
実家を共有名義で相続した後、ある相続人が亡くなるとその相続人の持ち分は、さらに子ども世代へと相続されます。亡くなった相続人に子どもが複数いる場合などは共有名義人の数が増えます。初めは兄弟たちで共有名義にしていたものが、子ども世代孫世代へと相続されるにつれて、名義人の数はどんどんと増えていく可能性があります。最終的には面識のない人同士でひとつの不動産を共有していたり、相続人が何人いるかも分からなくなったりすることも珍しくありません。そのような状態になると、売却や取り壊しなどに全員の同意を得ることは、ほぼ不可能になりますし、そもそも連絡先すら分からないことの方が多いでしょう。
共有名義になることを避ける方法
ここまで、実家を共有名義にすることには大きなリスクが伴うことをお伝えしました。実家に対する考えは、将来的なライフステージの変化などで変わることも十分に起こりえます。そのため、一時的な処置のつもりであっても共有名義にすることは避けた方がよいでしょう。ここからは、実家の相続人が複数いる場合に、共有名義にする以外の対応法を紹介します。
売却して現金を等分する
共有名義を避ける最もシンプルな方法は、売却して得たお金を相続人で等分するという方法です。土地と建物のどちらも手放すことができるので、その後の管理の手間や固定資産税のことを考える必要がなくなる点で大きなメリットがあります。
1人が相続し、代償金を残りの相続人に渡す
これは複数の相続人がいる中で1人が実家を相続し、残りの相続人に代償金を渡すことで平等に利益を得るというものです。例えば、相続人が3人いる実家の価値が900万円だとしたら、実家を相続する1人が残りの2人に実家の価値の3分の1となる300万円ずつを現金で渡すというものです。
この方法であれば3人が得る金銭的メリットは平等になります。しかし、相続する1人は、実家の価値によっては多くの現金が必要となるため、現実的に難しい場合もあります。代償金の支払いを分割にする方法も考えられますが、滞納リスクなどもあるためあまりおすすめできません。
自分の持ち分を売却する
実家そのものの売却には共有名義人全員の同意が必要となりますが、自分の持ち分については自由に売却できます。とはいえ、共有名義の実家の持ち分を一部得たとしても、実家を売却したり賃貸物件にしたりはできません。持ち分を購入してくれる専門業者もありますが、基本的に持ち分を購入しようとする第三者は限られます。
一般的なのは、共有名義人に持ち分を売却する方法です。例えば、共有名義人が自分を合わせて2人ならば、自分の持ち分を売却することで相手の単独所有となりますので、双方にメリットが生まれやすくなります。また、実家に住み続けたいという理由で売却に反対している名義人がいれば、自分の持ち分を買い取ってくれる可能性は大いにあります。持ち分の売却は、金銭的なメリットに加え、自分が共有名義人である状態から抜け出せる点でもメリットがあります。
自分の持ち分を贈与する
共有名義人または第三者に自分の持ち分を贈与する方法もあります。贈与は自分の意思だけでは成立せず贈与する相手の同意も必要です。贈与の際には贈与税がかかる可能性があることに注意が必要です。贈与する持ち分の評価額が110万円を超える場合、贈与税の対象となり、贈与を受けた側(持ち分をもらった側)が贈与税を支払うことになります。
自分の持ち分を放棄する
共有名義人となった後、自分が得た持ち分については放棄することも可能です。贈与と似ていますが、放棄の場合は、特定の誰かに持ち分を渡すのではなく、放棄された持ち分は残りの共有名義人がそれぞれの所有する持ち分の割合に合わせて平等に分配されます。ただし、持ち分放棄によって登記上の不動産名義を変更する際は、他の共有名義人と一緒に行う必要があります。相続税法上は、持ち分放棄も贈与とみなされるので、持ち分の評価額によっては贈与税が発生する点には注意が必要です。
また、放棄は共有名義人がいる際にのみ行えるもので、仮に自分以外の共有名義人が全員持ち分放棄し、自分が単独名義人となった場合は放棄できません。
実家の扱いは相続する前に決めておこう
実家を共有名義で相続することにはリスクやデメリットが大きく、相続人の子や孫の代までの懸念事項となる可能性を秘めています。これを避けるためには、相続が決まる前から、あらかじめ相続人となる人たちの間で話し合いをしておくことが重要です。最も避けるべきは、誰も住まず、そのまま空き家となってしまうことです。空き家となれば、相続人の誰にもメリットはありません。ぜひ今回のコラムを参考に、実家の今後について検討してみてください。
本コラムの内容は公開・更新時点の情報に基づいて作成されたものです。最新の統計や法令等が反映されていない場合がありますのでご注意ください。