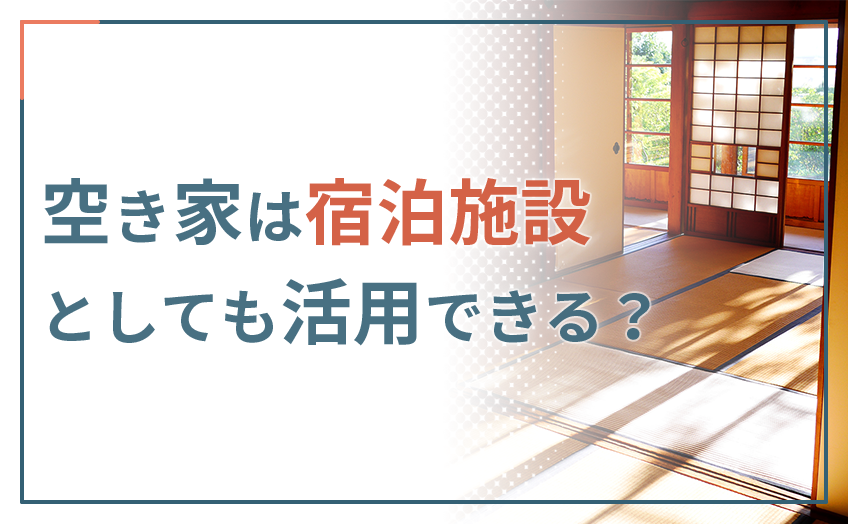相続した空き家などが放置され、衛生面や治安面での悪影響を周囲に及ぼす「空き家問題」に社会的な注目が集まり、国や各自治体もさまざまな対策を実施しています。
空き家をリフォームして自身が入居する、賃貸住宅にする、取り壊して更地にするなど、さまざまな活用方法がある中で、その実行には大きな費用がかかることがあります。
今回のコラムでは、空き家活用に使用できる補助金・助成金をテーマに、さまざまな事例を紹介していきます。ぜひ空き家活用のヒントにしてください。
国が実施している空き家活用の補助金(住宅セーフティネット法)
低額所得者や高齢者、被災者、障害者、子育て世帯、外国人などは、家賃滞納などのリスクから入居が断られるケースがあります。このような人々のことを住宅確保要配慮者(要配慮者)といいます。
国は、住宅セーフティネット制度に基づき、賃貸住宅を要配慮者の入居を拒まない住宅(セーフティネット住宅)に登録した場合、一定の要件で物件オーナーに対して改修費や家賃の支援を実施しています。
ここでの家賃支援とは、入居者から徴収する家賃を下げる代わりに、その減額した分を物件オーナーに直接支援するというものです。
戸建ての空き家を集合住宅へ間取り変更する際にも利用可能です。
次項より、基本的な条件や補助金額などについて紹介します。
参考:国土交通省 住宅セーフティネット制度
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html
セーフティネット住宅登録の条件
登録は各市区町村で行います。登録できる集合住宅の基本的な条件は以下の3つです。登録は1棟丸ごとでなくても、一戸単位で可能です。
- 床面積が25㎡以上
- 耐震性があること(新耐震基準に適合)
- 台所・便所・洗面・浴室等の設備があること
※シェアハウスの場合は別途条件あり。
ただし、上記の内容は自治体によって変更が可能なため、25㎡未満の住宅でも支援を受けられる可能性はあります。
また、セーフティネット住宅には、住宅の確保が難しい要配慮者も受け入れるが、一般の入居希望者も受け入れる「登録住宅」と、要配慮者のみが入居できる「専用住宅」の2種類があり、物件オーナーが直接経済的な支援を受けられるのは、専用住宅のみです。
専用住宅にする場合でも低額所得者や高齢者、被災者、障害者、子育て世帯、外国人といったあらゆる要配慮者を受け入れる必要はなく、高齢者のみ入居可能にすることや、障害者と低額所得者のみ入居可能な専用住宅にすることなども可能です。
物件オーナーへの支援内容
専用住宅にすることで受けられる、空き家活用に対する国からの経済的支援には「改修費への補助」「家賃低廉化への補助」の2つがあります。
- 改修費への補助
以下の工事にかかる費用が補助されます。
- ① 耐震改修
- ② 間取り変更
- ③ シェアハウスへの改修
- ④ バリアフリー改修
- ⑤ 居住のために最低限必要と認められた工事
- ⑥ 居住支援協議会等が必要と認める工事
- ⑦ これらに係る調査設計計画の作成
これらについて国と地方それぞれから一戸あたり最大50万円、合計100万円の補助が受けられます。補助率は国と地方合わせて2/3です。
また、①・②・③のいずれかを含む場合には、補助の限度額が倍になり、最大で200万円の補助が受けられます。
- 家賃低廉化への補助
これは、要配慮者のうち、月収15.8万円以下の低額所得者の入居を認める際に受けられる補助金です。低額所得者の負担を軽減するために、家賃を市場相場よりも減額した場合、その減額分が補助されます。
補助率は100%で、限度額は1戸あたり1ヶ月4万円(国・自治体が各2万円)です。例えば、相場家賃が7万円のところ、低額所得者からの家賃は3万円にしたら、減額した4万円が毎月オーナーに補助されることになります。補助期間は最長で10年です。
専用住宅に登録する際の注意点
一戸あたりで補助が受けられる専用住宅に登録することには、大きなメリットがあります。しかし、物件オーナーが受けられる「改修費への補助」「家賃低廉化への補助」の2つの補助のうち、改修費への補助を受けた際には以下のような制約が生まれる点には注意が必要です。
- 家賃の上限が定められる
国による改修費の直接補助を受けた場合には、10年間以上、公営住宅相当の家賃水準以下にする必要があります。上限家賃の算出は「67,500円×50/65×市町村立地係数」という式で求められます。
例えば、北海道札幌市なら上限家賃は51,900円、千葉県千葉市なら57,100円、東京都新宿区なら67,400円、愛知県名古屋市なら57,100円、大阪府大阪市なら64,900円です。
専用住宅のみへの支援
| 事業主体等 | 大家等 |
|---|---|
| 対象世帯 | 月収15.8万円以下の世帯 |
| 補助限度額 | 4万円/戸・月 等 |
| 支援期間 | 原則10年以内 等 |
| 国による直接補助 | 地方公共団体を通じた補助 | |
|---|---|---|
| 事業主体等 | 大家等 | |
| 補助対象工事 |
| |
| 補助率・補助限度額 | 1/3 | 2/3 |
| ①~⑥を実施する場合:100万円/戸 その他:50万円/戸 | ①~⑥を実施する場合:200万円/戸 その他:100万円/戸 | |
| 入居対象者 | 住宅確保要配慮者 | 住宅確保要配慮者(月収38.7万円以下 等) |
| 家賃 | 公営住宅に準じた家賃の額以下であること | 近傍同種家賃と均衡を失しない額であること |
| その他主な要件 | 専用住宅として10年以上管理すること | 専用住宅として10年以上管理すること。 ただし、一定の要件を満たす場合は住宅確保要配慮者以外も入居可能 |
参考:セーフティネット住宅情報提供システム 住宅セーフティネット制度とは
https://www.safetynet-jutaku.jp/docs/system_020.pdf
今回は国から受けられる補助金の一例を紹介しました。今回紹介したもの以外にも、戸建て・集合住宅を問わず、省エネ化のためのリフォームなどへの補助金が設けられています。国土交通省の以下のページにリフォーム支援の補助金がまとめてありますので、参考にしてください。
参考:国土交通省 住宅リフォームの支援制度 ※令和6年5月2日時点(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000087.html
自治体が実施している空き家活用の補助金の検索方法
ここまで、国が実施している、賃貸住宅への補助金の一例を紹介しました。ここからは、賃貸住宅としての活用ではなく、空き家の解体や管理にかかる費用に対して実施されている補助金を紹介します。
自治体から受けられる補助金は、補助率や上限額はもちろんのこと、条件もさまざまです。どのような補助金が設けられているのかは、「〇〇市 空き家 補助金」などと検索すると見つけやすいでしょう。
また、株式会社補助金ポータルが運営している「補助金ポータル」では、市区町村を絞って実施中の補助金が検索できます。利用目的も選択できるようになっており、「空き家利用」にチェックを入れると、調べたい自治体の、空き家利用に対しての補助金が一覧で表示され、非常に便利です。ただし、すべての補助金が網羅されているとは限らないため、必要に応じて市区町村の公式サイトも確認するようにしてください。
参考:補助金ポータル (株式会社補助金ポータル)
https://hojyokin-portal.jp/
空き家活用の補助金例(京都市)
自治体が実施している空き家活用への補助金には、「解体費用の補助」「仲介手数料の補助」「改修費用への補助」などがあります。改修費用への補助の場合は、空き家を店舗や事務所に改装するなど、用途が定められています。補助金は地域活性化のために設けられているので、改修費用への補助は多くの自治体が実施しており、比較的見つけやすいでしょう。
今回は空き家の活用補助金として少し珍しい「解体費用の補助」と「仲介手数料の補助」を行っている、京都市の例を紹介します。
解体費用の補助
上限を60万円に、解体費用の1/3が補助されます。解体後、敷地を隣の土地と1つにして50㎡をえる土地として利用する場合は、最大で20万円が加算されます。
補助の対象となる空き家の基本条件は以下の通りです。
- 昭和64年1月7日以前に建築
- 敷地面積が 50㎡以下
- 個人が所有
- 共同住宅は不可(戸建てが対象)
- 現在居住・使用していない。申請直前までの居住・使用は可。
- 解体後、敷地を活用(自身が利用または売却)する
仲介手数料の補助
これは、売却時に不動産会社に支払う仲介手数料を補助するものです。上限を25万円として、仲介手数料の1/2が補助されます。
仲介手数料は法律で「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限と定められているので、約1,300万円以上の売却になると満額の25万円が補助されることになります。
補助の対象となる空き家の基本条件は以下の通りです。
- 昭和64年1月7日以前に建築
- 延べ床面積が200m㎡以下
- 個人が所有
- 共同住宅は不可(戸建てが対象)
- 売却時に居住・使用していない。売却の直前まで居住・使用していたものも可。
参考:京都市情報館 【令和6年度】京都市空き家等の活用・流通補助金について
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000329679.html
住宅セーフティネット法に基づいて行われている空き家活用への補助金と異なり、自治体が実施している補助金には年度ごとの予算と申請期限があります。期限内でも補助した金額が予算の上限まで達した場合は、申請期限内でも終了してしまう点には注意が必要です。また、同じ補助金が翌年も実施されるかも分かりませんし、実施されたとしても補助内容や適用条件が変更されることがあります。
空き家をどのように活用するにしろ、補助金の申し込みはなるべく早く行うことを意識してください。年度の途中で始まる補助金も多くあるので、定期的に市区町村の公式サイトなどをチェックすることをおすすめします。
本コラムの内容は公開・更新時点の情報に基づいて作成されたものです。最新の統計や法令等が反映されていない場合がありますのでご注意ください。